| 2004(H16年)・・≪渓流一年生≫ |
|---|
| 2004(H16年)・・≪渓流一年生≫ |
|---|
忘れもしない5月3日が生涯初めての釣り・・・
そして5月23日三回目の釣行で初めての「ヤマメ23センチ」をキャッチ!!
そして7月9日には泣き尺の29.5センチをキャッチ!!(大喜)
しか〜し保存していた写真がパソコンの故障により完全消滅(大涙)
ということでこの年はこんなものをご紹介してみることにします
| 山陰中央新報に連載された「釣り フィッシングコーナー」の釣り旅日記 <根深 誠さん>をご紹介 ( ※ 写真も同時に掲載されたものを引用しています) シーズンが終わってから始まった連載は、私の中で「渓流」が大きく大きく夢あるものへと・・・・ 実は、第一回目は出張中だったので見逃し・・しかも記事がない(大涙) どなたかお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡お待ちしています(願) 第二回 ”やらずの渓”に漂う・・・・・・平成16年10月29日  対象魚によって、いろいろな種類の楽しみ方がある。私の場合、釣りといえば、対象魚はイワナ、ヤマメ、すなわち渓流釣りをさす。人煙絶えた深山幽谷から、ひなびた村落を流れる里川まで範囲はひろい。釣り方も、この四十年来、餌釣り、ルアーフィッシング、フライフィッシング、てんから釣り、さまざまな釣法を試みたが、いまは主として餌釣り、ときには気まぐれにてんから釣りを楽しむ。この間、飲酒や食べ物の嗜好品にかぎらず、遊びとしてのつりの世界も経験や年齢に伴い、好みに変化が生じることを知った。最近はめっきり足腰が衰え、テントを担いで奥山をめざし、”やらずの渓”(容易に近づけない難所の釣り場)で釣ることは少々つらい。歩行のバランスが悪くなった。先のシーズンにも、近くの、といっても車で小一時間かかる所だが、免許のない私は大学生の息子に乗せてもらって行き、そこそこ釣りを楽しんでから岩場で足元がふらつき転倒し、四つんばいの姿勢で流れに滑り落ち、上腕を擦りむいた。それに加えて、滑落した拍子にビクがひっくり返り、中に入っていたイワナ、ヤマメ十数尾と、川岸で摘み取ったミズ(山菜の一種)を流されてしまったのだ。谷間の下方に夕焼け空がひろがっていた。竿をたたみ、その空を眺めながら、いつものことだが、渓流釣りの魅力について考えた。そのキーワードは季節感と旅、または漂白といっていいかもしれない。釣り場を巡りつつ、自然との交感、自然との照応、それによって生の充逸を自覚し、自然界の摂理を知る。 対象魚によって、いろいろな種類の楽しみ方がある。私の場合、釣りといえば、対象魚はイワナ、ヤマメ、すなわち渓流釣りをさす。人煙絶えた深山幽谷から、ひなびた村落を流れる里川まで範囲はひろい。釣り方も、この四十年来、餌釣り、ルアーフィッシング、フライフィッシング、てんから釣り、さまざまな釣法を試みたが、いまは主として餌釣り、ときには気まぐれにてんから釣りを楽しむ。この間、飲酒や食べ物の嗜好品にかぎらず、遊びとしてのつりの世界も経験や年齢に伴い、好みに変化が生じることを知った。最近はめっきり足腰が衰え、テントを担いで奥山をめざし、”やらずの渓”(容易に近づけない難所の釣り場)で釣ることは少々つらい。歩行のバランスが悪くなった。先のシーズンにも、近くの、といっても車で小一時間かかる所だが、免許のない私は大学生の息子に乗せてもらって行き、そこそこ釣りを楽しんでから岩場で足元がふらつき転倒し、四つんばいの姿勢で流れに滑り落ち、上腕を擦りむいた。それに加えて、滑落した拍子にビクがひっくり返り、中に入っていたイワナ、ヤマメ十数尾と、川岸で摘み取ったミズ(山菜の一種)を流されてしまったのだ。谷間の下方に夕焼け空がひろがっていた。竿をたたみ、その空を眺めながら、いつものことだが、渓流釣りの魅力について考えた。そのキーワードは季節感と旅、または漂白といっていいかもしれない。釣り場を巡りつつ、自然との交感、自然との照応、それによって生の充逸を自覚し、自然界の摂理を知る。第三回 ”四国のアマゴ釣り”・・・・・・平成16年11月5日  四国の川が総じて、きれいな印象を与えるのは、広い河原があるからだと思った。その白く乾いた河原を眺めて思い起こしたのは少年時代のことだった。昔は私の郷里の川にも瓦が残っていたような記憶がある。その河原で、近くの畑からくすねてきたジャガイモや、ヤスで突いたカジカをたき火で焼いて食べたりした。川で水遊びをしたり、ときには死人が出たりもしたけれど、川は確かに遊び場の一部であり、生きていたのだった。川にかぎらず、自然が生活の一端を担うような環境であれば、自然にに対する人々の無頓着な意識が目覚め、この国の環境問題はよりよい方向へ前進するに違いない。が、現代社会はあまりのも自然から遊離している。せめて、一竿の風月に身を託すゆとりはないものであろうか。そんな思いで私は釣り巡っている。そして、美しい風景と出会ったとき心がほのかに満たされるのだ。四国の渓流でアマゴ釣りを楽しんだときもそうだった。夕暮れ時、上流の谷間に四国の最高峰石鎚山がどっしりした山容を見せていた。渓流釣りの用語で「夕まずめ」というのだが、薄闇のころが絶好の状態だ。私は六・二メートルの長竿を使って、幅広い流れの深みのある瀬で振り込みを繰り返した。ガツンとアタリがあって、中型のアマゴが勢いよく、次々と掛ってきた。小渓流の繊細な釣りと異なり、川岸の草木にハリを引っかける心配もなかった。まぁまぁ、これは改心の釣りといえるだろう、と私は内心ほくそ笑み、周囲の風景を見まわしながら旅情に浸った。 四国の川が総じて、きれいな印象を与えるのは、広い河原があるからだと思った。その白く乾いた河原を眺めて思い起こしたのは少年時代のことだった。昔は私の郷里の川にも瓦が残っていたような記憶がある。その河原で、近くの畑からくすねてきたジャガイモや、ヤスで突いたカジカをたき火で焼いて食べたりした。川で水遊びをしたり、ときには死人が出たりもしたけれど、川は確かに遊び場の一部であり、生きていたのだった。川にかぎらず、自然が生活の一端を担うような環境であれば、自然にに対する人々の無頓着な意識が目覚め、この国の環境問題はよりよい方向へ前進するに違いない。が、現代社会はあまりのも自然から遊離している。せめて、一竿の風月に身を託すゆとりはないものであろうか。そんな思いで私は釣り巡っている。そして、美しい風景と出会ったとき心がほのかに満たされるのだ。四国の渓流でアマゴ釣りを楽しんだときもそうだった。夕暮れ時、上流の谷間に四国の最高峰石鎚山がどっしりした山容を見せていた。渓流釣りの用語で「夕まずめ」というのだが、薄闇のころが絶好の状態だ。私は六・二メートルの長竿を使って、幅広い流れの深みのある瀬で振り込みを繰り返した。ガツンとアタリがあって、中型のアマゴが勢いよく、次々と掛ってきた。小渓流の繊細な釣りと異なり、川岸の草木にハリを引っかける心配もなかった。まぁまぁ、これは改心の釣りといえるだろう、と私は内心ほくそ笑み、周囲の風景を見まわしながら旅情に浸った。第四回 ”地酒と釣り人”・・・・・・平成16年11月12日  渓流釣りの好きな人には酒好きが少なくない。自分の舌で酒を玩味し、品定めができるようになるには、釣りと同じように年季が要る。伯耆大山の釣行で急流に磨かれた、釣果のイワナの美しさもさらなることながら、なにより地酒がおいしかった。私はその地酒を、大山のふもとにある、スギの巨木に囲まれた宿に泊まり・一風呂浴びた浴衣姿で独酌したのだった。四合瓶である。夏の夕焼け空が、スギ木立のむこうにひろがっていた。それは切ないほどの、とろけるような深紅に染まった空の色だった。旅の空から見る自然の風光は慈悲深く叙情的である。あくる朝、地元のIさんの案内で入渓し、私はイワナト戯れるひとときを過ごした。Iさんの釣法は私と同じ餌釣りだったが、仕掛けが若干異なる。私が極小のオモリをつけて餌を流れに巻き込ませるのに対し、Iさんは親指大のオモリをつけて、泡立つ深みにドボンと水音をたてて沈めるのだ。そのときの衝撃で、場所によってはイワナが逸走することもあるという。私たちは源流地帯まで釣り上った。私の釣り方がIさんには華麗に映ったようだ。後年、Iさんと会ったとき、しばらくの間、まねてみたが、やっぱり元に戻ったと笑いながら話していた。大山の急峻な山地渓流にはIさんの仕掛けが合っているのだろう。あのとき私たちは釣行を終えたのち酒を酌み交わし、旧交を温めたものだが、山陰地方には値段も手ごろで、私の味覚に適っている地酒が多いようだ。 渓流釣りの好きな人には酒好きが少なくない。自分の舌で酒を玩味し、品定めができるようになるには、釣りと同じように年季が要る。伯耆大山の釣行で急流に磨かれた、釣果のイワナの美しさもさらなることながら、なにより地酒がおいしかった。私はその地酒を、大山のふもとにある、スギの巨木に囲まれた宿に泊まり・一風呂浴びた浴衣姿で独酌したのだった。四合瓶である。夏の夕焼け空が、スギ木立のむこうにひろがっていた。それは切ないほどの、とろけるような深紅に染まった空の色だった。旅の空から見る自然の風光は慈悲深く叙情的である。あくる朝、地元のIさんの案内で入渓し、私はイワナト戯れるひとときを過ごした。Iさんの釣法は私と同じ餌釣りだったが、仕掛けが若干異なる。私が極小のオモリをつけて餌を流れに巻き込ませるのに対し、Iさんは親指大のオモリをつけて、泡立つ深みにドボンと水音をたてて沈めるのだ。そのときの衝撃で、場所によってはイワナが逸走することもあるという。私たちは源流地帯まで釣り上った。私の釣り方がIさんには華麗に映ったようだ。後年、Iさんと会ったとき、しばらくの間、まねてみたが、やっぱり元に戻ったと笑いながら話していた。大山の急峻な山地渓流にはIさんの仕掛けが合っているのだろう。あのとき私たちは釣行を終えたのち酒を酌み交わし、旧交を温めたものだが、山陰地方には値段も手ごろで、私の味覚に適っている地酒が多いようだ。第五回 ”郡上八幡の珍味”・・・・・・平成16年11月19日  郡上八幡の居酒屋で、アマゴの塩焼きをさかなに酒を飲んだことがある。私が釣ったアマゴを、店の女将が焼いてくれたのだ。アマゴはヤマメの仲間であり、降海性のものがサツキマスと呼ばれている。ヤマメと形態は似ているが、魚体に朱紅点がちりばめられている点が異なる。天然の生息分布域もまたヤマメと異なる。私が郡上八幡で釣ったアマゴは、小型がたったの二尾、まさしく貧果に終わった釣行だった。その二尾の釣果を、旅の釣り客に焼いてくれた女将の厚意はありがたい。私は釣り旅に出てもガイドブックを持参するわけでなく、行き当たりばったり式で道中、出会った人にぶっきらぼうにたずねるのだ。地方の町や村では、たいがい心当たりがあるらしく親切に教えてくれる。その居酒屋の女将の父親は名代の釣り名人であり、情報たるや、十分過ぎるほどだった。その情報をもとにして、私は吉田川の支流に入渓したのだ。上流では川岸にヨシが茂り、古い堰があり、遠くの民家のたたずまいといい、典雅な風景を見せていた。それにしても、私の貧果を見て、女将は驚いたようだ。まさか露骨に、あんた、ヘタやねぇ、ともいえないだろうし、いまごろの季節はそんなものですよ、と感想を述べた。後年、そのときお世話になったお礼に拙著を贈呈すると、女将は郡上八幡の珍味「みたたき」を返礼に贈ってくれた。野鳥を細かくたたいて、しょうゆで味付けしたものだ。私はそのような珍味があることを知らなかった。はじめて賞味し、その独特の風味に感激した。 郡上八幡の居酒屋で、アマゴの塩焼きをさかなに酒を飲んだことがある。私が釣ったアマゴを、店の女将が焼いてくれたのだ。アマゴはヤマメの仲間であり、降海性のものがサツキマスと呼ばれている。ヤマメと形態は似ているが、魚体に朱紅点がちりばめられている点が異なる。天然の生息分布域もまたヤマメと異なる。私が郡上八幡で釣ったアマゴは、小型がたったの二尾、まさしく貧果に終わった釣行だった。その二尾の釣果を、旅の釣り客に焼いてくれた女将の厚意はありがたい。私は釣り旅に出てもガイドブックを持参するわけでなく、行き当たりばったり式で道中、出会った人にぶっきらぼうにたずねるのだ。地方の町や村では、たいがい心当たりがあるらしく親切に教えてくれる。その居酒屋の女将の父親は名代の釣り名人であり、情報たるや、十分過ぎるほどだった。その情報をもとにして、私は吉田川の支流に入渓したのだ。上流では川岸にヨシが茂り、古い堰があり、遠くの民家のたたずまいといい、典雅な風景を見せていた。それにしても、私の貧果を見て、女将は驚いたようだ。まさか露骨に、あんた、ヘタやねぇ、ともいえないだろうし、いまごろの季節はそんなものですよ、と感想を述べた。後年、そのときお世話になったお礼に拙著を贈呈すると、女将は郡上八幡の珍味「みたたき」を返礼に贈ってくれた。野鳥を細かくたたいて、しょうゆで味付けしたものだ。私はそのような珍味があることを知らなかった。はじめて賞味し、その独特の風味に感激した。第六回 ”無心の子に導かれ”・・・・・・平成16年11月26日  椎葉村(宮崎県)をたずねたとき、小一時間ほどだったが、釣り好きな小学生が川を案内してくれた。その小学生は、このシーズン中に尺ヤマメを二尾釣ったと誇らしげに語った。聞いただけで、それはすごい。私は自分のことのようにその話に感激した。その時の少年の興奮状態が、手に取るようにわかるのだ。その小学生は地元だけに、おそらく朝な夕な川に出かけ、それに加えて父親や近所の大人からも情報を得て、質量ろもに豊かな情報を身につけているのだった。が、それだけでいい釣りができるとはかぎらない。私のも経験があるが、釣技の巧拙はともかく、どうしたわけか、無心になっているとき大物が掛かる。無心に遊ぶことにかけて大人は子供の比でない。子どものほうがそうした能力ははるかにたけている。最近の仮想現実社会では、都会のどもは、そうした能力が退化しているようだ。それよりなにより最近は、見知らぬ大人と子どもが歩くこと自体、犯罪の臭いをはらんだ危険性がつきまとい、あきらかに誤解を招く。小学生は私を、自分が尺ヤマメを釣った、いわば”穴場”に案内した。が、あいにく、このときは雨上がりの増水時で、とても釣りにならなかった。いかにも大物が潜んでいそうな大淵だが、状態が悪すぎる。場所を変えて、手ごろな渓流を案内してもらい、私は小学生に手ほどきしながらヤマメをつってみせた。小学生は私の腕前におおいに感激し、私は大人気もなく得意然とした気持ちになったのだ。 椎葉村(宮崎県)をたずねたとき、小一時間ほどだったが、釣り好きな小学生が川を案内してくれた。その小学生は、このシーズン中に尺ヤマメを二尾釣ったと誇らしげに語った。聞いただけで、それはすごい。私は自分のことのようにその話に感激した。その時の少年の興奮状態が、手に取るようにわかるのだ。その小学生は地元だけに、おそらく朝な夕な川に出かけ、それに加えて父親や近所の大人からも情報を得て、質量ろもに豊かな情報を身につけているのだった。が、それだけでいい釣りができるとはかぎらない。私のも経験があるが、釣技の巧拙はともかく、どうしたわけか、無心になっているとき大物が掛かる。無心に遊ぶことにかけて大人は子供の比でない。子どものほうがそうした能力ははるかにたけている。最近の仮想現実社会では、都会のどもは、そうした能力が退化しているようだ。それよりなにより最近は、見知らぬ大人と子どもが歩くこと自体、犯罪の臭いをはらんだ危険性がつきまとい、あきらかに誤解を招く。小学生は私を、自分が尺ヤマメを釣った、いわば”穴場”に案内した。が、あいにく、このときは雨上がりの増水時で、とても釣りにならなかった。いかにも大物が潜んでいそうな大淵だが、状態が悪すぎる。場所を変えて、手ごろな渓流を案内してもらい、私は小学生に手ほどきしながらヤマメをつってみせた。小学生は私の腕前におおいに感激し、私は大人気もなく得意然とした気持ちになったのだ。第七回 ”昔懐かしい情趣”・・・・・・平成16年12月3日  広瀬川の上流にある山峡の、とある無人駅のまん前の食堂に泊めてもらうことにした。食堂の壁にはイワナ・ヤマメの魚拓が飾られてあった。主人も、その父親も、そのまた父親、つまり祖父も釣り好きで、釣り客にかぎって泊めているのだった。その親子は代々、渓流釣りに親しんできたわけである。おそらく陸封型の渓魚と同じように、この家族もまた陸封されて生活をしてきたのに違いないと私は考えた。渓流釣りにはひなびた風情がつきまとう。それは過疎の村や廃村であったり、人煙絶えた深山幽谷であったりする。渓魚にはきらびやかで人工的な環境は不似合いなのだ。酒をすすりながら釣り談義をしていると、近くの踏み切りにある警報機がチンチンと鳴って、通過する列車の音がゴトゴトと響いてくる。そこには忘れかけていた昔懐かしい情趣があった。釣り談義といえば、古きよき時代に尽きる。昔はカワマスが上がってきたものだが、とか、そういえばカワネズミを見なくなった、などど語り合った。あくる朝、宿の主人が握ったおにぎりをザックにしのばせ、教えてもらった道をたどって入渓した。清冽な流れに立つと心がなごむ。私は釣り支度を整え、渓(たに)をさかのぼった。各ポイントで小型、といっても手のひらサイズのイワナ・ヤマメがかかった。まもなく魚止めの滝が現れた。そこには大物が入っているでしょう、と宿の主人が話していたが、滝ツボは不気味なほどの深さであり、岩場に取り囲まれた大きな淵だ。私の三・二メートルのてんから竿ではとても歯がたたなかった。 広瀬川の上流にある山峡の、とある無人駅のまん前の食堂に泊めてもらうことにした。食堂の壁にはイワナ・ヤマメの魚拓が飾られてあった。主人も、その父親も、そのまた父親、つまり祖父も釣り好きで、釣り客にかぎって泊めているのだった。その親子は代々、渓流釣りに親しんできたわけである。おそらく陸封型の渓魚と同じように、この家族もまた陸封されて生活をしてきたのに違いないと私は考えた。渓流釣りにはひなびた風情がつきまとう。それは過疎の村や廃村であったり、人煙絶えた深山幽谷であったりする。渓魚にはきらびやかで人工的な環境は不似合いなのだ。酒をすすりながら釣り談義をしていると、近くの踏み切りにある警報機がチンチンと鳴って、通過する列車の音がゴトゴトと響いてくる。そこには忘れかけていた昔懐かしい情趣があった。釣り談義といえば、古きよき時代に尽きる。昔はカワマスが上がってきたものだが、とか、そういえばカワネズミを見なくなった、などど語り合った。あくる朝、宿の主人が握ったおにぎりをザックにしのばせ、教えてもらった道をたどって入渓した。清冽な流れに立つと心がなごむ。私は釣り支度を整え、渓(たに)をさかのぼった。各ポイントで小型、といっても手のひらサイズのイワナ・ヤマメがかかった。まもなく魚止めの滝が現れた。そこには大物が入っているでしょう、と宿の主人が話していたが、滝ツボは不気味なほどの深さであり、岩場に取り囲まれた大きな淵だ。私の三・二メートルのてんから竿ではとても歯がたたなかった。第八回 ”マタギ集落の釣り名人”・・・・・・平成16年12月10日 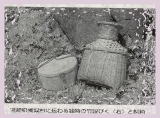 下北半島の形状をマサカリにたとえれば、金属部分の真ん中付近に畑という集落がある。ここは、正真正銘の伝承的マタギの里であり、つい最近まで、狩猟伝承の戒律や習俗が生活の中に脈々と息づいていた。マタギ伝承の本を書くため、私がこの村に通い続けていたころ、イワナ釣り名人の老爺が二人いた。二人とも釣法が異なる。一人はバッタが餌、一人はカジカを疑似餌にして使う。二人に共通しているのは、かけ損ねたり、バラしたりすることが、ほとんどないことだった。私の場合早合わせで、掛け損ねたり、とり込み中にバラすことがたびたびある。機会は別だったが、二人の名人と釣行をともにしたとき、私はそれぞれにたずねた。「バラしたりすることはないのですか?」「もちろん、それはあるよ、百回にいっぺんほどかな」という内容の同じ答えが返ってきた。バッタを餌にして釣る名人は、ミチイトの先端に直接ハリを結び、バッタを背掛けにして、小刻みにアクションをつけて水面を引く。他方、カジカを擬似餌にして釣る名人の釣法は、カジカの頭部をちょん切り、内部の臓物をしぼりだし、皮だけの胴体を筒状に膨らませ、中にハリを通して尻部から先端を出す。このあと胴体の入り口をミチイトでしばってふさぎ、中から空気が漏れないようにする。それを水面に振り込んで引くとくるくる回転し、背びれが光る。イワナは色めき立ち、それに食らいつくというわけだ。釣行時の、二人の元気な笑顔が懐かしく思い出される。 下北半島の形状をマサカリにたとえれば、金属部分の真ん中付近に畑という集落がある。ここは、正真正銘の伝承的マタギの里であり、つい最近まで、狩猟伝承の戒律や習俗が生活の中に脈々と息づいていた。マタギ伝承の本を書くため、私がこの村に通い続けていたころ、イワナ釣り名人の老爺が二人いた。二人とも釣法が異なる。一人はバッタが餌、一人はカジカを疑似餌にして使う。二人に共通しているのは、かけ損ねたり、バラしたりすることが、ほとんどないことだった。私の場合早合わせで、掛け損ねたり、とり込み中にバラすことがたびたびある。機会は別だったが、二人の名人と釣行をともにしたとき、私はそれぞれにたずねた。「バラしたりすることはないのですか?」「もちろん、それはあるよ、百回にいっぺんほどかな」という内容の同じ答えが返ってきた。バッタを餌にして釣る名人は、ミチイトの先端に直接ハリを結び、バッタを背掛けにして、小刻みにアクションをつけて水面を引く。他方、カジカを擬似餌にして釣る名人の釣法は、カジカの頭部をちょん切り、内部の臓物をしぼりだし、皮だけの胴体を筒状に膨らませ、中にハリを通して尻部から先端を出す。このあと胴体の入り口をミチイトでしばってふさぎ、中から空気が漏れないようにする。それを水面に振り込んで引くとくるくる回転し、背びれが光る。イワナは色めき立ち、それに食らいつくというわけだ。釣行時の、二人の元気な笑顔が懐かしく思い出される。第九回 ”釣り人の心象風景”・・・・・・平成16年12月17日  草むらの小道をたどり、川岸に出ると、二人の釣り人が目の前で上流の淵をねらっていた。軽い会釈を交わし、思わず私は下流に目をそらした。見知らぬ他人から見られていると集中力を失い、釣りにくいことを体験的に知っているからだ。小渓流なので、上流に回って先釣りするわけにもいかないし、下流に釣り下ろうかと逡巡していると、二人の釣り人は、川を上がりますからどうぞ、と私に声をかけて竿をたたみ、私が来た道を引き返していった。一人になると、道南の小渓流のまばゆい空が心に染みる。川岸に繁茂するイタドリをかき分け、淵の上流に出て釣り上がった。小さなイワナ・ヤマメが入れ食いの状態だった。あとで知ったけれど、地元の名人によれば、水量がいつもの倍ほどに増えていたのだった。それでなのか、魚の居場所が散らばっていた。しかも、ハリの掛かり具合が浅く、バラすことが多かった。私はそれを防ぐため、ハリスを短くし、ハリ先にひねりを加えた。そうすることで合わせが早くなり、ハリ掛かりもよくなる。が、それが本当かどうかは定かではない。そのように想像し、とくに大振りのできない小渓流では、こうした小細工を施すことが、釣りのテクニックとして身についてしまっているのだ。釣り人はまた、川の自然にも敏感である。動植物の動き、風の肌ざわり、葉ずれの響き、クマに出くわすのではないかという緊張感、そうしたもろもろの心象風景がときめきとなり、釣り人に生きていることを実感させる。 草むらの小道をたどり、川岸に出ると、二人の釣り人が目の前で上流の淵をねらっていた。軽い会釈を交わし、思わず私は下流に目をそらした。見知らぬ他人から見られていると集中力を失い、釣りにくいことを体験的に知っているからだ。小渓流なので、上流に回って先釣りするわけにもいかないし、下流に釣り下ろうかと逡巡していると、二人の釣り人は、川を上がりますからどうぞ、と私に声をかけて竿をたたみ、私が来た道を引き返していった。一人になると、道南の小渓流のまばゆい空が心に染みる。川岸に繁茂するイタドリをかき分け、淵の上流に出て釣り上がった。小さなイワナ・ヤマメが入れ食いの状態だった。あとで知ったけれど、地元の名人によれば、水量がいつもの倍ほどに増えていたのだった。それでなのか、魚の居場所が散らばっていた。しかも、ハリの掛かり具合が浅く、バラすことが多かった。私はそれを防ぐため、ハリスを短くし、ハリ先にひねりを加えた。そうすることで合わせが早くなり、ハリ掛かりもよくなる。が、それが本当かどうかは定かではない。そのように想像し、とくに大振りのできない小渓流では、こうした小細工を施すことが、釣りのテクニックとして身についてしまっているのだ。釣り人はまた、川の自然にも敏感である。動植物の動き、風の肌ざわり、葉ずれの響き、クマに出くわすのではないかという緊張感、そうしたもろもろの心象風景がときめきとなり、釣り人に生きていることを実感させる。第十回 ”知床の豊饒な渓”・・・・・・平成16年12月24日  尺ヤマメがかかると、心臓がドキドキしてしまう。興奮のきわみに達し、鼓動が高鳴り、頭がクラクラする。若いころはヒザがガクガクして足先にまで緊張感が走ったものだが、さすがにいまは年の功というべきか、そのようなことはない。しかし、イトがピンと張って竿がしなり、ときにはイト鳴りがして、かかったヤマメが激しく逸走するたびに、イトが切れるのではないかと心配で気が気でない。知床半島に出かけたときのことだが、水量といい、その色といい、ほれぼれするような渓相にめぎり会った。季節は秋口、産卵遡上のサクラマスにヤマメが寄り添い、水中で定位していた。それが何組もいるのだ。私は目をむいた。なんという豊かな川なのか、まさに豊饒の渓(たに)。毛バリを打ち込むと、ギューンと穂先が絞り込まれる。そのアタリの鋭敏さからヤマメであることを察知した。しかも、これはでかい。うまくあやしながら瀬尻に回って、砂地の岸辺に引きずり上げた。鼻曲がりの、精悍な顔つきをした見事な尺ヤマメではないか。それが驚くなかれ、同じ淵で、ひとつ、ふたつ、みっつ、入れ食い状態を呈したのだ。六尾釣って、こんどは荒瀬の岩陰に毛バリを振り込んだ。ドツンと強烈なアタリがあった。毛バリをくわえ込んだ魚体は、段差のある急流をものともせず一直線に逸走した。竿はのされてしまい、なすすべもなくイトはプツンと切れた。サクラマスに違いなかった。ため息をつきながら空を仰ぐと、白い尾羽をつけた海ワシがオホーツクホーツク海のほうへ谷間の空を横切った。 尺ヤマメがかかると、心臓がドキドキしてしまう。興奮のきわみに達し、鼓動が高鳴り、頭がクラクラする。若いころはヒザがガクガクして足先にまで緊張感が走ったものだが、さすがにいまは年の功というべきか、そのようなことはない。しかし、イトがピンと張って竿がしなり、ときにはイト鳴りがして、かかったヤマメが激しく逸走するたびに、イトが切れるのではないかと心配で気が気でない。知床半島に出かけたときのことだが、水量といい、その色といい、ほれぼれするような渓相にめぎり会った。季節は秋口、産卵遡上のサクラマスにヤマメが寄り添い、水中で定位していた。それが何組もいるのだ。私は目をむいた。なんという豊かな川なのか、まさに豊饒の渓(たに)。毛バリを打ち込むと、ギューンと穂先が絞り込まれる。そのアタリの鋭敏さからヤマメであることを察知した。しかも、これはでかい。うまくあやしながら瀬尻に回って、砂地の岸辺に引きずり上げた。鼻曲がりの、精悍な顔つきをした見事な尺ヤマメではないか。それが驚くなかれ、同じ淵で、ひとつ、ふたつ、みっつ、入れ食い状態を呈したのだ。六尾釣って、こんどは荒瀬の岩陰に毛バリを振り込んだ。ドツンと強烈なアタリがあった。毛バリをくわえ込んだ魚体は、段差のある急流をものともせず一直線に逸走した。竿はのされてしまい、なすすべもなくイトはプツンと切れた。サクラマスに違いなかった。ため息をつきながら空を仰ぐと、白い尾羽をつけた海ワシがオホーツクホーツク海のほうへ谷間の空を横切った。 |